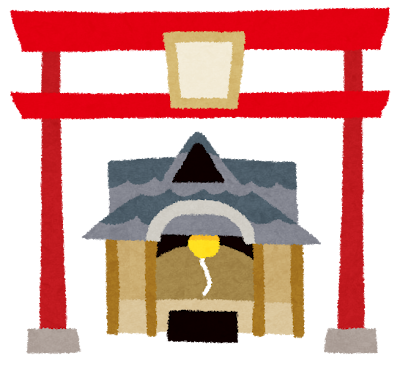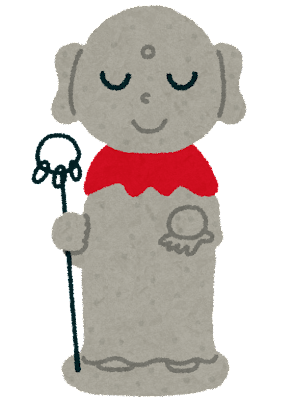Contents
『東京農業歴史めぐり』:過去に参拝しました『江戸・東京の農業』の説明板がある寺社をまとめてみました
江戸・東京の農業:江戸東京野菜
東京の寺社を参拝していると、
『江戸・東京の農業』と書かれた黒い看板を目にすることがあります。
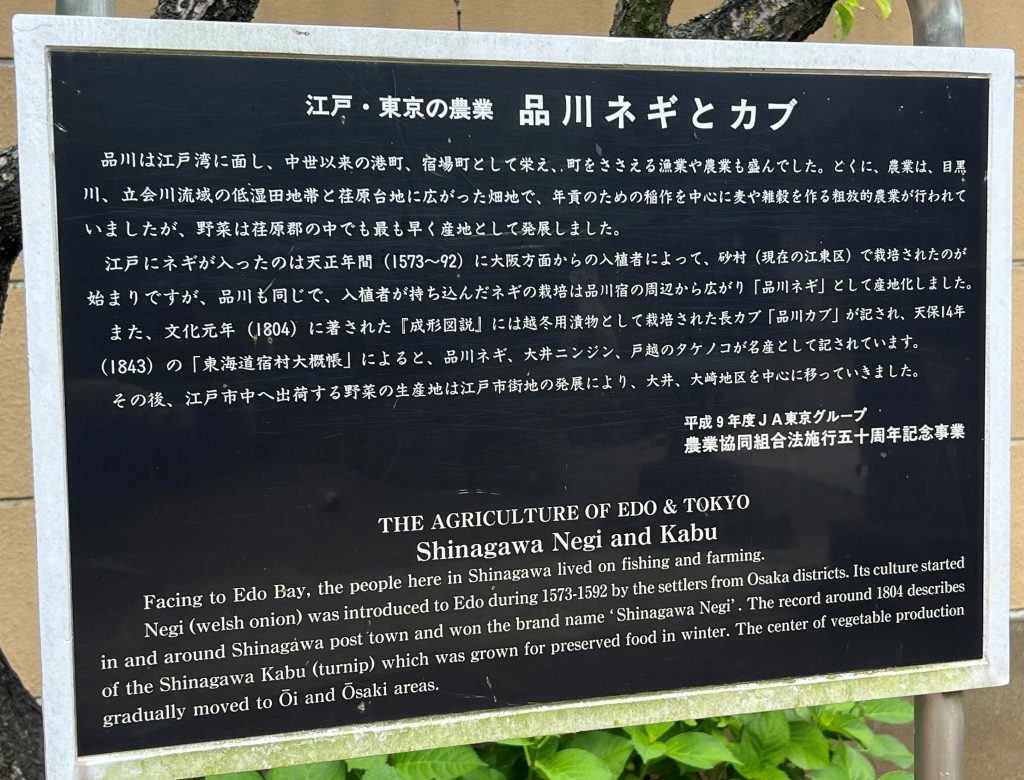
平成九年(1997年)にJA東京グループが農業協同組合法施行50周年記念事業として、
東京都神社庁などとの協力により、
『江戸・東京の農業野外説明板』が都内50箇所に設定されています。
参照HP:JA東京中央会『東京農業歴史めぐり』
https://www.tokyo-ja.or.jp/farm/edomap/
今では希少価値のある農産物についてや、
寺社のある地域とのゆかりについても知ることができます。
東京都豊島区
眞性寺(しんしょうじ):旧中山道はタネ屋街道
農家の副業としてタネを販売するようになり、
巣鴨のとげぬき地蔵から板橋区清水町にいたる約六キロの間に、
タネ屋問屋や小売店が立ち並び、さながらタネ屋街道になっていました。
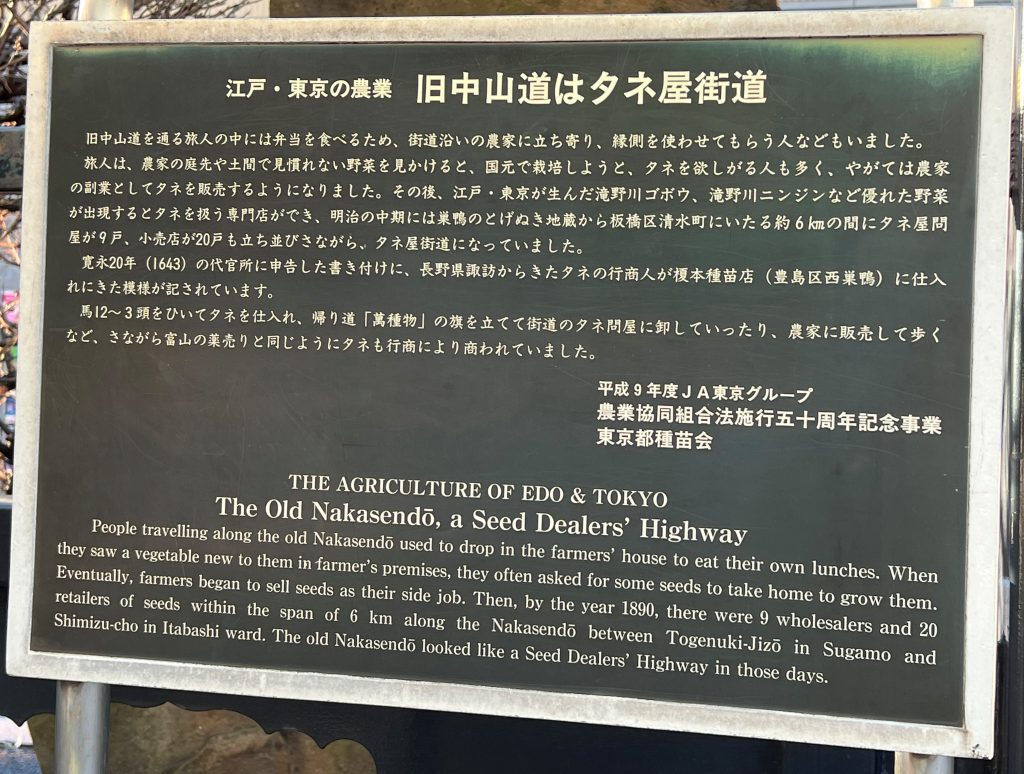
雑司が谷大鳥神社(おおとりじんじゃ):雑司ヶ谷ナス
このあたりは雑司ヶ谷ナスの産地として有名でした。
味がいいと評判で、江戸時代後半から大正時代の中頃までもてはやされていました。
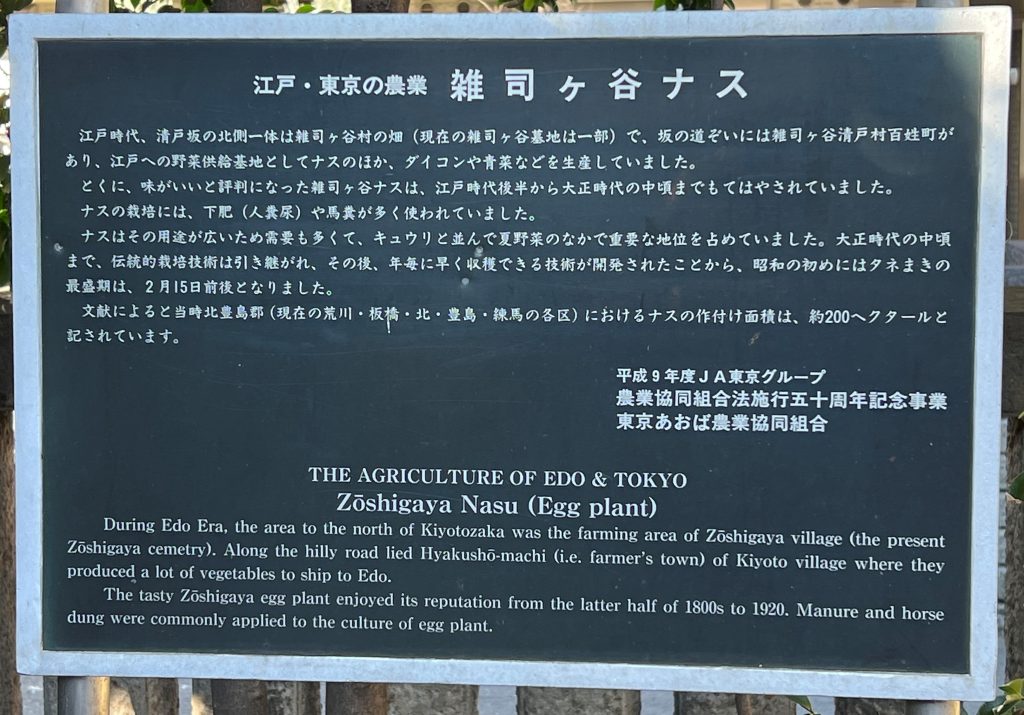
東京都新宿区
成子天神社(なるこてんじんしゃ):鳴子ウリ
神社の地域は江戸時代はマクワウリの産地でした。
元禄十一年(1698年)に新宿に市場が開かれた為、
栽培が盛んになったそうです。鳴子坂の地名から鳴子ウリとも言われました。
甘味が多く、水菓子として貴重な野菜でした。
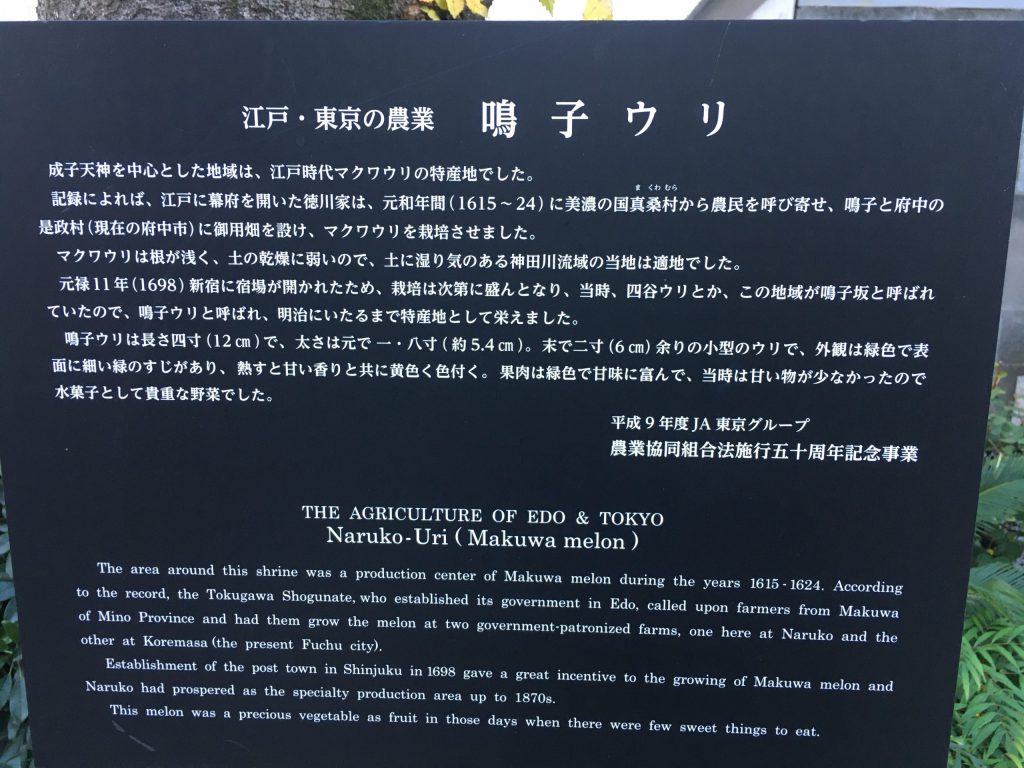
東京都中野区
中野沼袋氷川神社(ひかわじんじゃ):東京大越瓜(とうきょうおおしろうり)
沼袋は江戸時代から昭和初期まで、越瓜(しろうり)の特産地でした。
漬物も今のようにきゅうりではなく、越瓜(しろうり)に限られました。
大越瓜(おおしろうり)は奈良漬けとしても有名です。
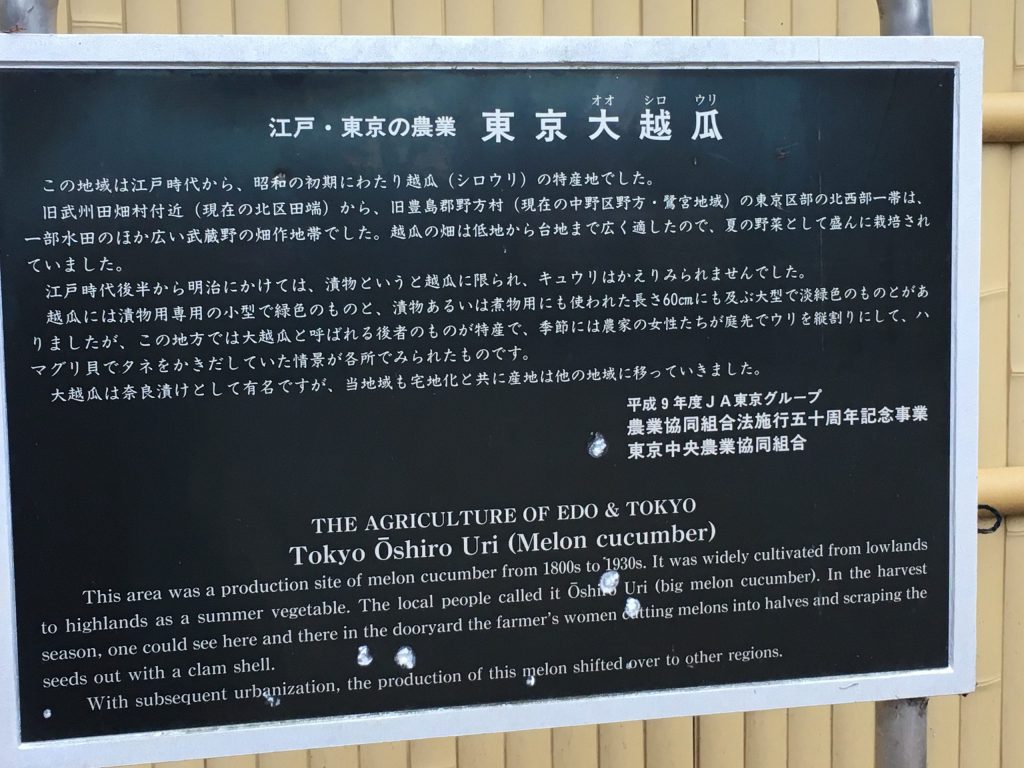
東京都杉並区
井草八幡宮(いぐさはちまんぐう):井荻ウド
ウドは数少ない日本原産の野菜で、江戸時代後期にはこの地域でも栽培されました。
文政年間(1818年~30年)に古谷岩右衛門が尾張で栽培法を習い、
一帯に広まっていきました。
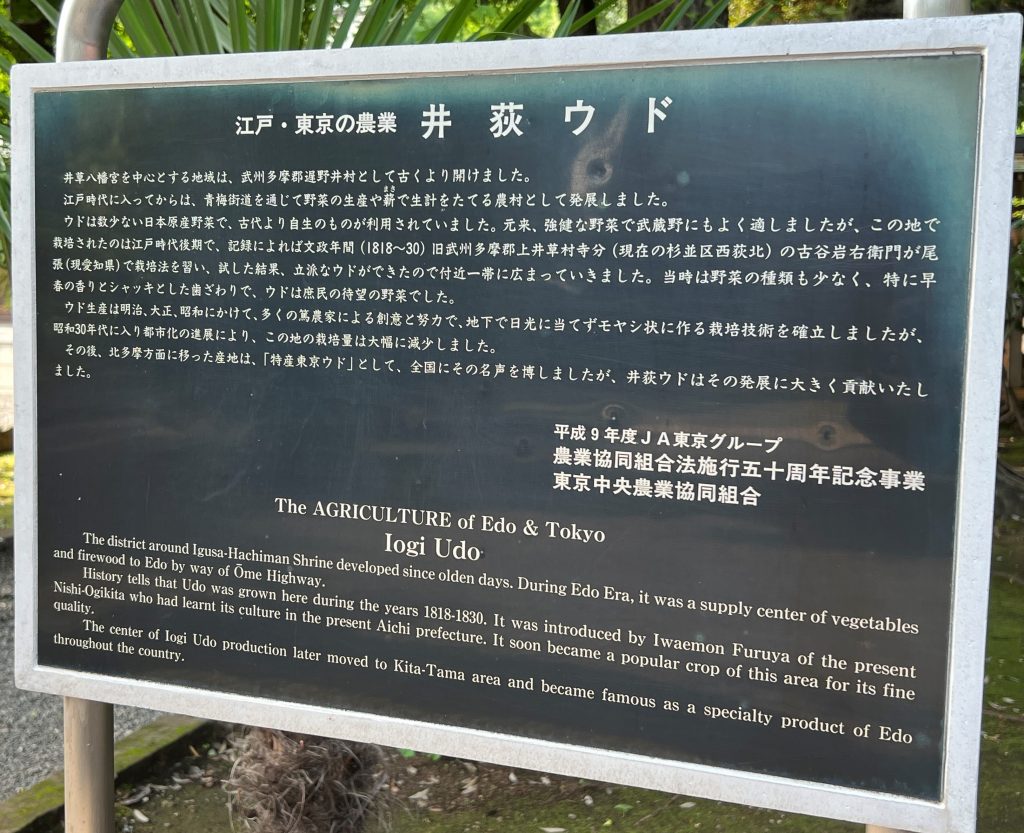
東京都江東区
亀戸香取神社(かめいどかとりじんじゃ):亀戸大根
文久年間(1861年~64年)の頃から大根づくりが始まり、
特に亀戸香取神社周辺が栽培の中心地でした。
大正初期に産地の名をつけて『亀戸大根』と呼ばれるようになりました。
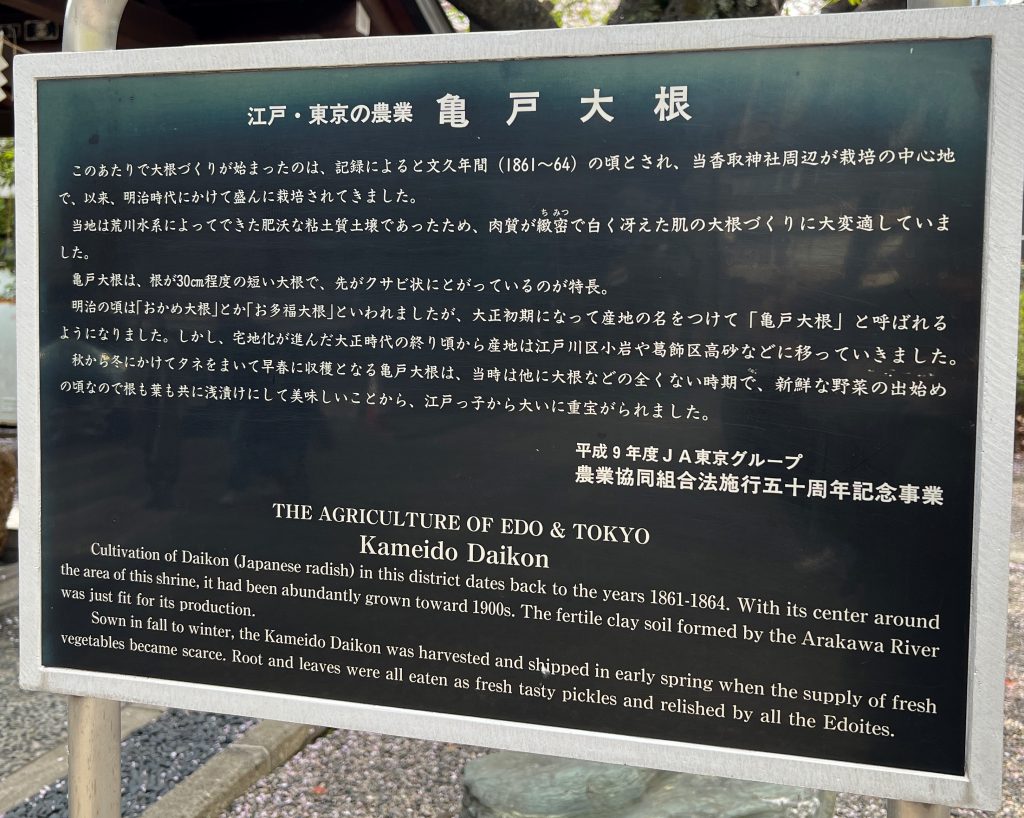
東京都品川区
品川神社(しながわじんじゃ):品川ネギとカブ
天正年間(1573年~1592年)に大阪方面からの入植者によって栽培されたネギは、
品川宿周辺から広がり、『品川ネギ』として産地化しました。
また越冬用漬物として長カブ『品川カブ』も栽培されました。
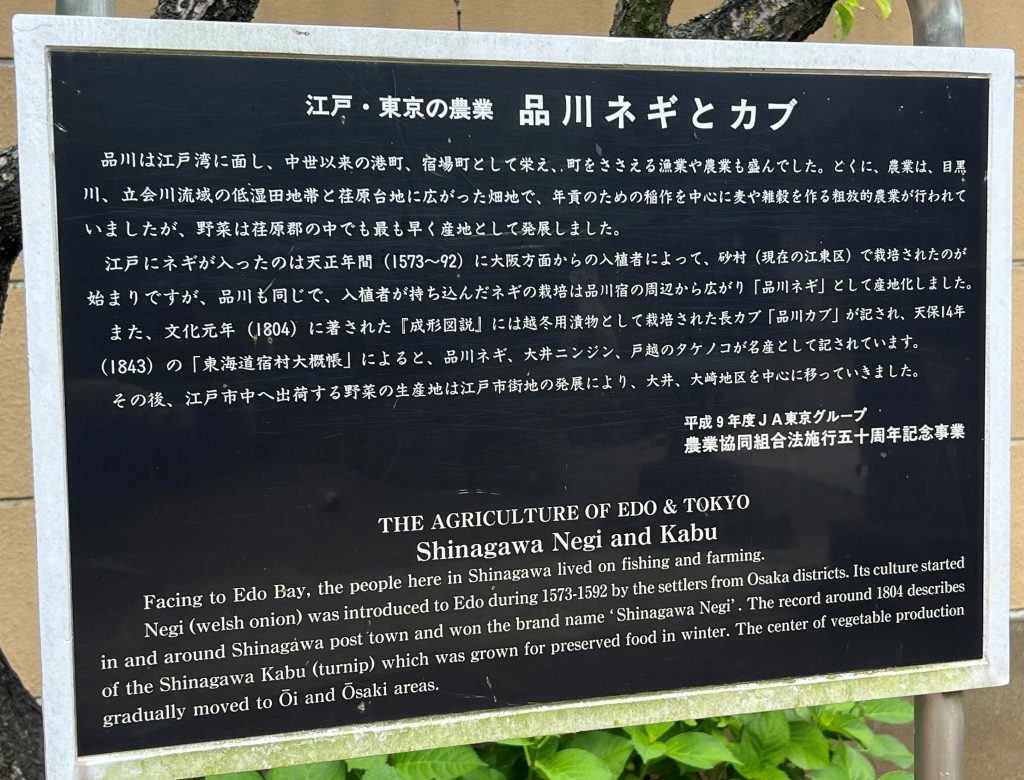
東京都武蔵野市
武蔵野八幡宮(むさしのはちまんぐう):吉祥寺ウド
吉祥寺ウドは、江戸時代後期の天保年間(1830年~44年)頃に栽培されるようになりました。
冬から春にかけて野菜が不足していたことから、この時期に生産されたウドは、
独特の歯ざわりと香りで、江戸庶民に歓迎されました。
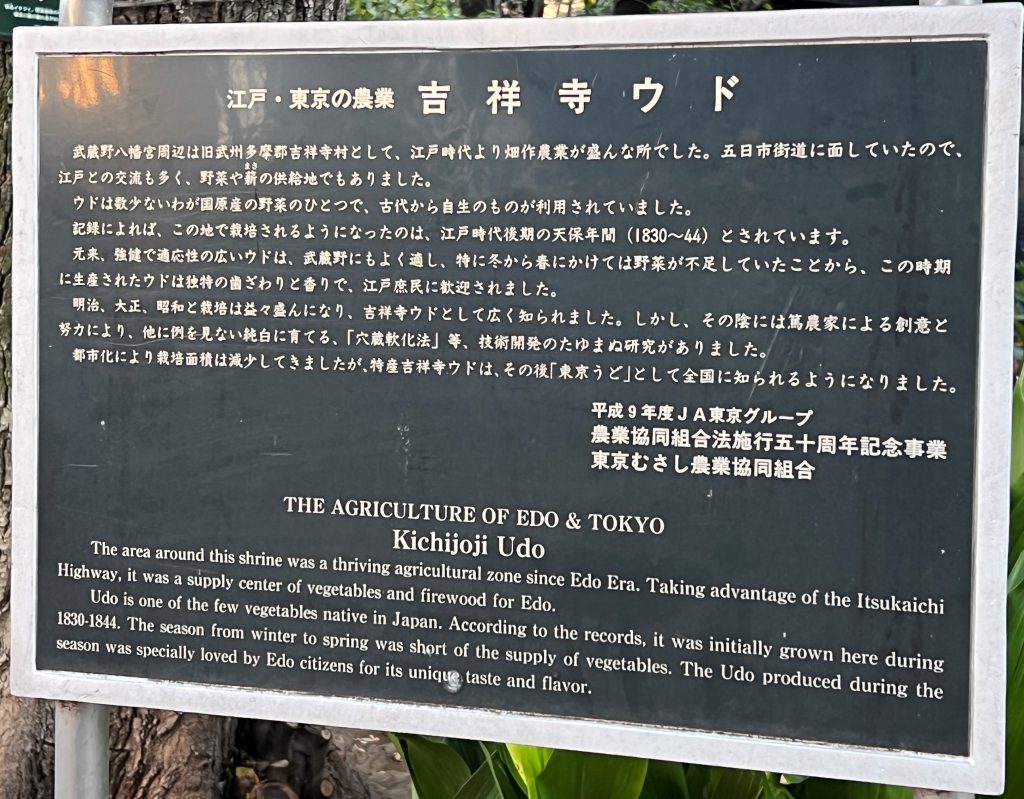
東京都羽村市
武蔵阿蘇神社(あそじんじゃ):養蚕の村・羽村
羽村は8世紀初頭に養蚕と機織りが行われていましたが、
盛んになったのは江戸時代になってからで、明治に入って養蚕先進地となり、
大正時代には収穫量日本一を自負したといわれました。
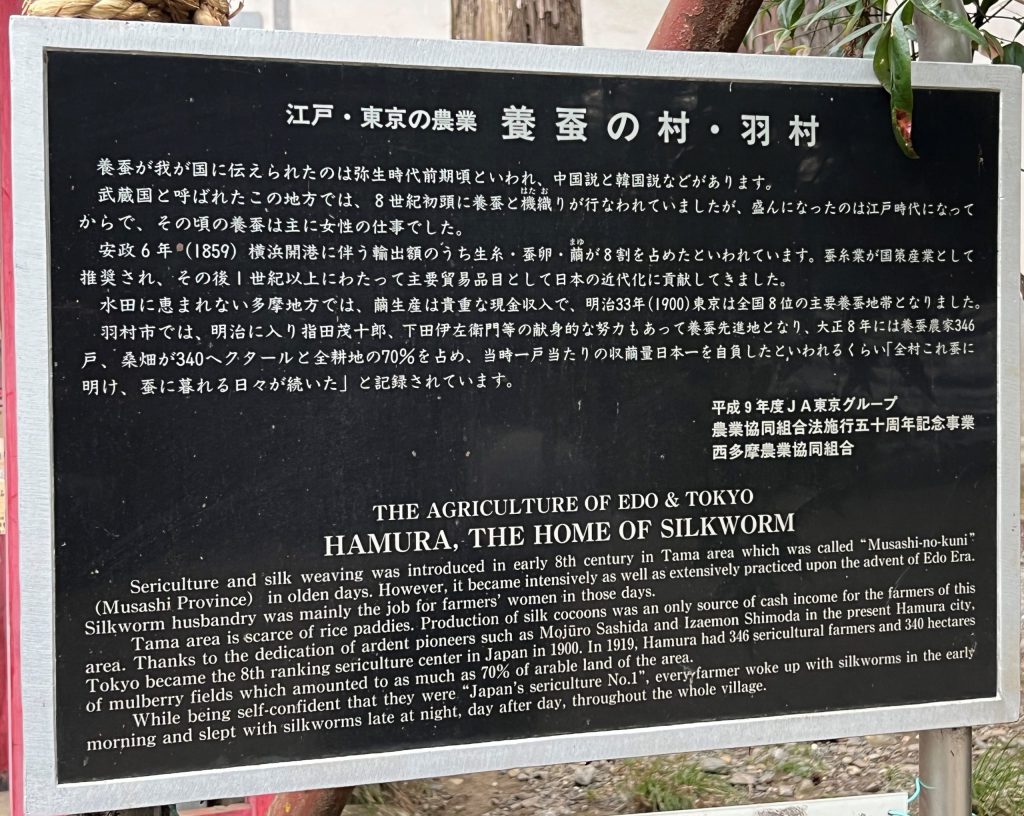
ご覧頂きましてありがとうございます。